貧しい、と聞いてどのようなイメージを抱きますか?私は、住む家がなかったり、衣服はボロボロ、常にお腹が減っているようなイメージです。
豊か、と聞いてどのようなイメージですか?先程の反対でいえば、食べる物に困らず、買いたい物が買え、家電が揃っていて便利な暮らしを送っているイメージとなります。
けれども、私はそうは思わないという話です。
何不自由ないのに感じていた「どこか物足りない」高校生時代の私
高校生くらいから、なにか物足りない感を持ち続けています。当時、父親は、教員をしていて、母親は、専業主婦でした。家はホームメーカーの二世帯住宅で、習い事も存分にさせてもらえていました。毎日3食保障され、お腹が減れば冷蔵庫の中のものを、母親に確認してつまんでいました。決して裕福ではないけれど、何不自由ない生活でした。
でも、何でしょうね。勉強や習い事で、努力したり達成感を得たり、周りから評価されることもありましたが、どこか満たされないものがありました。
幼少期の母とのやさしい会話にあった「絶対的な安心感」とは
では、満たされているな、と感じた場面を遡ると、幼少期に夜布団の上でしていた母との会話の場面です。
「どうして風邪をひくの?」「どうして体は大きくなるの?」とか、体や病気のことについて気になることを母に質問して、その都度、母が優しい口調で応えてくれていました。その時に、安心や尊敬で満たされ「僕はお母さんの子どもで良かった」と伝えていることを覚えています。
ちなみに、会話の内容や母親の様子は、ほとんど覚えていません。けれども満たされていた自分の心の状態がとても温かいものに包まれていたことをよく覚えています。ここに自分が求めている豊かさのヒントがある気がしています。
それは、物の豊かさではないのは確かです。当時は、手狭なオンボロ家で、買いたいものがあっても、親に「お金がないから」と言い聞かされ、その状況を受け入れていました。
何か、絶対的な安心感や、ほわほわと包まれるものでした。
その状態を、「しあわせ感」を得ていると仮定します。 つまり、私の求める豊かさとは、親子の中でしあわせ感を得ることといえます。
しあわせ感はウェルビーイングの一部であり、単なる「嬉しい」「楽しい」といった感情だけでなく、健康、社会的関係、人生の意味、自己成長など複数の側面から成り立っています。持続的でバランスの良い「良い状態」がウェルビーイングとしてのしあわせ感の本質です。
保育を学び、子育てを経験して気づいた「求める豊かさ」とは何か
高校生時代からなんとなく、そのようなことを思っていたのでしょう。
大学は、乳幼児のことについて学ぶことを選びました。
卒業論文のテーマは、「父親でも母親に代わって子育てができる」というもの。
保育教育者として15年以上働き、愛着を育むことや、家庭機能不全による子どもを支えたいという分野への関心が高いです。
その間、結婚もしました。子どもも生まれ、「子どもにとっていい父親になりたい」と強く思うようになりました。
自分が求めていたしあわせ感は、子どもに味わってほしいと願うようになりました。
しかし、現実そう簡単なものではありませんでした。
妻も、子どもも、自分も「しんどい」「苦しい」「疲れた」と言うことばかりで、家庭機能不全に陥っている現状を自覚しながらも、何が要因でそうなっているのもはっきりと分からず、しあわせ感を求めながらも、どうすればそれを得られるのかが誰も分からなくなってしまっていました。
メンタル不調で休業を経験し気づいた「豊かさ」とはしあわせ感の共有
そんな中でも、事態が好転し始めた出来事がありました。
それは、自身のメンタル不調による休業です。
短い間でしたが、暮らしの中から「仕事」の要素を考えなくてよくなりました。
そして、豊かに暮らしたいという願いに気付くことができました。
豊かさについては、考えても考えてもなかなか答えが見つかりませんし、おそらくこれからも探し続けると思います。
でも、1つ分かったことは、「物質的なものではなく、しあわせ感を家族みんなで得ることなんだということ」です。
こうやって人生を振り返ってみると、見えてくるものがありますね。
最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。また、お会いしましょう。それまでお元気で。


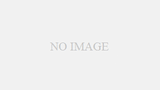
コメント